「Athlete Career Challenge カンファレンス2025」~競技の枠を超えアスリートと共に考えるアスリートの未来~
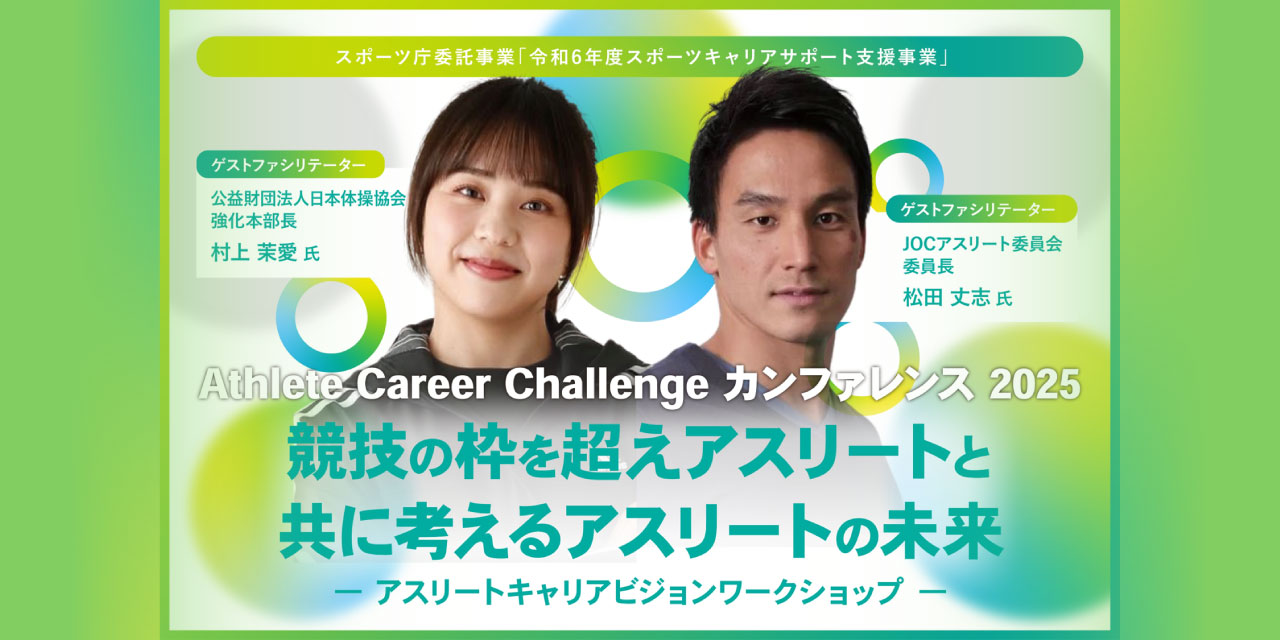

アスリートであれば、いつか訪れるのが“現役引退”です。引退を自分の意志で選択できる人もいれば、ケガなどにより突然引退を余儀なくされてしまう人もいます。アスリートには引退後も見据えた人生設計が必要であり、そのためには現役時代からのキャリア形成がとても重要といえます。
2017年2月、スポーツ庁は委託事業の一環として、スポーツキャリアサポートコンソーシアム(以下、SCSC)を創設し、産官学が一体となってアスリートのキャリア形成を支援する体制の整備を進めてきました。今年2025年2月26日、SCSC主催のアスリートキャリアをテーマにした「Athlete Career Challenge カンファレンス2025」が開催されましたので、その様子をレポートします。
Athlete Career Challenge カンファレンス2025とは
「Athlete Career Challenge カンファレンス」とは、SCSCの支援活動を通じて得られたアスリートを取り巻く環境や実例をもとに、スポーツ団体等におけるキャリア支援施策の事例紹介、アスリートのキャリア支援に精通した専門家たちによるトークセッション、アスリート人材を採用した企業によるリアルな話が聴けるなど、貴重な機会となっています。2021年から始まり、今年で5回目を迎えました。
2025年度の「Athlete Career Challenge カンファレンス2025」は、都内会場とオンラインのハイブリッド形式で行われ、現役アスリートや元アスリート、アスリートを支える立場の人等、900人以上が参加する注目度の高いカンファレンスとなりました。
カンファレンスは、3つのプログラムで進行されました。
PROGRAM1:アスリートのキャリア課題とは何なのか
PROGRAM2:アスリートと考えるキャリアビジョンワークショップ
PROGRAM3:アスリート人材に期待するチカラ
過去のカンファレンスでは、講座や座談会など、アスリートや指導者などに向けた情報提供がメインでしたが、今回から、アスリート自身によるグループセッションが取り入れられ、アスリート同士、アスリートと指導者、アスリートと企業など、双方向の意見交換を行うことができたことが大きな特徴といえます。
今回、ファシリテーターとして、水泳で2004年アテネ五輪から日本代表として4大会連続出場し4個のメダルを獲得した松田丈志さん(JOCアスリート委員会委員長)、体操女子個人で日本史上初のメダリストの村上茉愛さん(公益財団法人日本体操協会教科本部長)を迎え、ご自身の経験談などを披露しながら各コーナーの進行を担われました。
カンファレンスの副題「競技の枠を超えてアスリートと共に考えるアスリートの未来」のとおり、アスリートキャリアの今後をアスリート自身が考える機会となりました。
なお、カンファレンス冒頭ではスポーツ庁室伏長官による挨拶及びスポーツ庁の取り組み紹介がありました。室伏長官は、競技と研究を両立した自身の経験を踏まえ、スポーツの価値を社会全体に拡張する重要性を強調しました。スポーツ界の透明性向上、アンチ・ドーピングの推進、競技拠点強化の取り組み、トップアスリートの知見を活かして一般の運動機能向上や高齢者の健康維持に貢献する科学的アプローチを紹介しました。
また、JAXAとの連携を通じ、スポーツと宇宙開発の共通点を指摘し、パラアスリートを含む競技者の適応能力が宇宙飛行士の育成に役立つ可能性についても述べました。「一器多様」の概念のもとで新たなスポーツの可能性を探り、スポーツの枠を超えた挑戦が未来の人類の発展に貢献すると語りました。





PROGRAM1:アスリートのキャリア課題とは何なのか
PROGRAM1では、アスリートのキャリア課題について、一般社団法人日本プロサッカー選手会マネージャー・小林慎一朗さん、公益財団法人日本陸上競技連盟専務理事・田﨑博道さんが登壇され、それぞれの取組についてプレゼンテーションが行われ、キャリア課題について質疑応答が行われました。
日本プロサッカー選手会では、予期せぬトランジッション(ケガ、契約・移籍、環境変化、若手の成長など)が多く、引退時期が早いプロサッカー選手に対し、“セカンドキャリア”という言葉は使わず、“1つのキャリア”としてサポートを行っていると言います。選手会主導で行っているPLAYER DEVELOPMENT PROGRAM(PDP)に関しては、選手の現役生活中から、スキルアップや引退後のキャリアやコネクション作りの相談などをサポートする体制を整えている現状をご紹介いただきました。(PDPは現在、女子選手を対象にパイロット版を2023年から始動)
小林さんは「アスリートが引退に対する恐れや不安を躊躇なく打ち明けられる環境を整備することは非常に重要であり、選手会では、賛同企業とともに様々な施策を検討している段階です。」と選手会の引退を身近に感じる選手へ寄り添う姿勢の大切さを説きました。また、「サッカー以外にも自身のスキルアップを考えることで、将来の不安を軽減させ、選手としてのパフォーマンスの向上につながる可能性もある。」と、自身のキャリア形成を考えることが、結果的に選手としてのレベルアップにつながる可能性をサッカー界全体で考えることが重要であると説明しました。
続けて登壇された田﨑さんには、日本陸上連盟が取り組んでいる、「ライフスキルトレーニングプログラム」に関してご紹介いただきました。今年で6年目を迎えるこのプログラムは、企業・アスリート・指導者それぞれが持つ課題を統括競技団体の立場から支援していくことをテーマに取り組んでおり、アスリートの強みとして田﨑さんは「アスリートは競技生活の中で壁を感じた時、それを突破するために新たな練習を試し技術を取得する、つまりイノベーションを起こす力があり、かつそれを粘り強く続け、試行錯誤する、タフネスも備えている。これらは、社会に置き換えても希少なスキルであり、アスリートこそ、イノベーションを起こす人材になり得る。」と説き、アスリートが普段の競技生活で自然と身に着けるスキルが、社会に可能性をもたらすことを紹介しました。
二人の話を聞いた村上さんからは、「選手と指導が”セカンドキャリア”についての話題になったとき、指導者に意識はなくとも、選手目線としては“もう選手として見られていないのかもしれない”という否定的にとらえる人も出てきてしまうかもしれない。指導者や支援していく立場として、学ぶことも大事だし、言葉の言い回しなど伝え方話し方にも気を使っていかなければならないと感じた。」とキャリアサポートの目線を選手目線に合わせていくこと、そして選手ケアに注意を払い、ポジティブな話題として捉えることの重要性に関して、気づきをいただきました。
また、松田さんからは「日本社会全体として、人材の流動性に課題があると感じている。その中でアスリートの現役には必ず終わりが来る。アスリートという人材の可能性は、イノベーションを起こす可能性と人材の流動性、それぞれ観点から社会問題解決に大きく寄与できるのではないか。」と、社会の課題にアスリートがどう携わり、支えられるかという視点でプログラムを締めくくりました。


PROGRAM2:アスリートと考えるキャリアビジョンワークショップ
PROGRAM2では、元体操選手の岡﨑美穂さん(有限会社レジックスポーツ代表取締役)と、進行役としてキャリアカウンセラーの川島隆一さん(川島事務所代表)が登壇し、参加アスリートによるグループディスカッションが行われました。ディスカッションはオンラインでも参加できる仕組みとなっています。
会場では1グループ4人前後でディスカッションが行われ、最初は互いに自己紹介を行うウォーミングアップからスタート。いくつかの対話テーマに対して、制限時間内にグループ内で意見交換を行い、ディスカッションの中で印象的な意見は、テーマの区切りごとにスクリーンに意見が映し出され参加者全員に共有されます。
テーマの設問に対して、グループ以外の参加者やオンライン参加者もパソコンやスマートフォンから入力でき、会場のスクリーンに意見が表示されていきます。さらに意見のなかで使われることが多かったキーワードがリアルタイムに次々と現れ、意見の流れが視覚化される仕組みを導入し、ディスカッションの活性化が図られました。
テーマは以下となります。
対話①アスリートのキャリアに関して問題だと思うことは?
対話②その問題の解決のために必要なことは?



プログラム中、岡﨑美穂さんからご自身が指導するレジックスポーツでの事例紹介がありました。レジックスポーツは中高生の体操選手育成を中心に指導しています。体操選手はセカンドキャリアで苦労している選手が多いといわれており、ジュニア期からキャリアを考えさせるキャリア教育に取り組んでいます。レジックスポーツでは、「人となり、競技者となろう」をスローガンに、子どもたち自身で人生と競技のデュアルキャリアを学び、保護者のサポート含めた体制や考えを軸に据えているといいます。競技面でのパフォーマンス向上と人生における知見を得る大切さは密接な相関関係があり、これらを両立させていくことが重要だとお話しいただきました。

ディスカッションではアスリートたちによる積極的な意見交換が行われ、「学生から社会人にステージが上がる際、競技を続けていくビジョンが見えない」や、「アスリートとしてのキャリアを詰めきれていないのに、セカンドキャリアを考えることにギャップがある」などの問題意識や、アスリート側の俯瞰的意見としても「競技力向上のため、PDCAサイクルを当たり前のように回してきたことで、自分が持つ課題解決能力の高さに気づけていないこと」や、「気合い・やる気・体力 = 営業職というような固定概念も重なり、社会の印象とアスリート人材の能力の認識のミスマッチを修正していくことが必要」など様々な意見が出ました。今回のワークショップは、アスリートの「生の声」を多くの人が共有し、それぞれが何か行動を起こすためのスタートラインになったかもしれません。
PROGRAM3:アスリート人材に期待するチカラ
PROGRAM3では、アスリートのセカンドキャリアを支える民間企業から、ソニー生命保険株式会社 中村仁さん、イオンモール株式会社 岡本章世さん、株式会社リクルート 近藤裕さん、3名に登壇していただき、各社によるアスリート人材に対する取組み・考え方についてお話ししていただきました。
中村さんは「アスリートを応援したい企業は多いが、次のステップとなる支援となると、メリットと財政的な面が現実として関わってくる。アスリートと企業をマッチングしつつ、その際にアスリートを支援するメリットを強く説くとともに、それに掛かる資金を企業財務コンサルティングの面からサポートすることで、今ある原資を有効活用するお手伝いをしていきたい。」と企業とアスリートが直面する現実に深く向き合った事業をご紹介いただきました。
続けて、登壇した岡本さんからは、地域のスポーツ団体と協業することで、地域を盛り上げスポーツの発展を両立していく事業のなかで、アスリートが今まで接してきた人、及びその関係性を地域社会に置き換え、「ファン=お客様」、「練習=仕事」とし、競技の発展と地域社会発展は互いに好影響をもたらすという企業視点を発表いただきました。
最後に登壇いただいたリクルートの近藤さんは、アスリートが持つ、”個” の力の大切さと強みが社会や企業において大きな力を発揮する事例をご紹介いただきました。チームスポーツで培ったチームワークや、課題に立ち向かう姿勢、新たなアプローチを見つける発想力、結果に対して振り返り、次の課題を見出すPDCAのサイクルの常習性など、アスリートが持つマインドが、仕事に対して非常に高い親和性をもつことを、実際にリクルートで活躍されている方々の具体例でお話しいただきました。
最後にすべての発表を聞いた村上さんは、「現役を終えたタイミングでこういうキャリアに関する知識を得る場面に出会いたかった。今日話を聞いて、キャリア形成に困っているアスリートに対して共有すべき知見を得て、大変有意義な時間を過ごすことができました。」と締めくくりました。



まとめ
カンファレンスでは、全プログラムを通じて、アスリート・競技団体・企業、それぞれからの視点で、アスリートのセカンドキャリアの現状と可能性について語られました。その話を聞くと「セカンドキャリア」は引退後のこととして捉えられてしまいますが、キャリアは現役選手時代からの延長線上にあることがわかります。現役アスリート、そして元アスリートの皆さん、「アスリートとしてのキャリア」と「人としてのキャリア」を両輪で考え、行動し今後の人生を歩んではいかがでしょうか。
そしてアスリートを支える立場の皆さんは二つのキャリアの両立を支え、アスリート自らの可能性を最大限に発揮するための環境を創出し、アスリートの持つ価値を社会に広めましょう。スポーツ庁では、これからもアスリートのキャリア形成を支援していきたいと思います。

●本記事は以下の資料を参照しています
スポーツ庁 - スポーツキャリアサポート支援事業(2025-03-01閲覧)
スポーツキャリアサポートコンソーシアム(2025-03-01閲覧)
スポーツキャリアサポートコンソーシアム(SCSC)キャリアセンター(2025-03-01閲覧)



